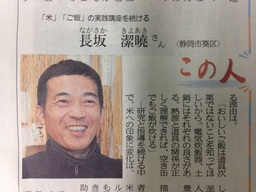安東米店店主との対話
12月2日地方版の静岡版「この人」に登場した安東米店(静岡市葵区)店主の長坂潔曉さん。藤枝生まれの新品種の可能性を探る「カミアカリドリーム勉強会」、水田と人間の関わりを考える「アートロ」など、米をキーワードにした多彩な活動で知られる長坂さん。さまざまな分野への示唆に富んだ、インタビューになりました。(橋)
(安東米店の創業期について)
「大正期、祖父とその兄はいろいろな商売をしていました。祖父は長谷通りかいわいで一番大きかった青木さんというお米屋さんで修行後、独立。結婚を機に現在の場所に店を構えた。浅間さんの山に上って『ここだ』と見定めたと聞いています。ちょうど、この土地に家を建てる第1世代でした。当時は、周囲に家がなくて、臨済寺の山門も、城北高校の一本松も全部見えていたそうです」
(米やご飯の講座を始めたきっかけについて)
「30歳までは、毎日営業してたくさん売ってくることしか考えなかった。でも、だんだん米粒がどうやって生まれ、どうやってここに来て、どう化学反応してご飯になるかを知らないことに気が付いてしまったんです。種もみからご飯までのうちの、『米』しか知らない。僕はその前後も知りたくなっちゃった。それで本を調べたり、人に出会ったり。そのうちお米マイスターの仕組みができあがって。外部の人と少しずつ接点ができて、今やっているようなことが始まりました」
(米の力について)
「1つの種もみが成長して、1000倍、1500倍になるんです。すごいと思いませんか。永遠のインフレーション。だから、これが何なのかということが分からないとパニックになる。ある意味『際物』だと分かった上で扱わないと。東アジアの人は、これを主要穀物として2000年以上生きている。お米のデンプンをエネルギーの源として、国家を作ってきた。そう思うと、米屋が考える範疇を超えるんですよね、実は」
(炊飯の実践を差す造語『スイハニング』について)
「お米をアルファ化して、食べられるデンプンにする。これが炊飯です。熱と水と時間があれば、お米は必ずご飯になるんです。道具の良しあしじゃありません。ただ、相性はあります。まきなら金属、ガスなら土物のほうがいいかな。熱源と道具の関係がわかれば、空き缶だって、お皿だってご飯が炊けます。盲点を作らないことが大切です」
(約30年、米に関わって気づいたこと)
「米作りは、コントロールを間違わなければ、永遠に続けていける技術。太陽がある限り、田んぼからお茶わんまでの営みは永遠に続けられる。結局、稲作とは何なのかというところですよ。田んぼって、人工的に作ったものの中で一番美しい。これほど美しいものはない。自然と調和し、なおかつ自然のままでいるより豊かになっている。人類が生み出した最高の芸術作品だと思いますね」
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.at-s.com/mt1/mt-tb.cgi/49134