2013年07月26日(金)付 朝刊
□パネル討論
パネル討論は「NIEのすそ野を広げるために」をテーマに、教育現場で新聞を活用するための課題や方策を議論した。NIEに携わる教諭、家庭での活用を考える保護者のほか、初の試みとして小中高校生もパネリストとして参加。教材として活用する学校だけでなく、児童生徒や保護者、取り組みを伝える新聞社が、さらにNIEの役割を認識し、魅力を伝え合い、情報発信する大切さが指摘された。
■現状-授業活用の時機逃す/家庭でも低い認知度/難解な語句がネック
・矢沢和宏さん 静岡はNIE発祥の地。学ぶ子供たちの考えから出発することがNIEの未来を開くと考え、小、中、高生をパネリストに迎えました。まず自己紹介をしてもらいます。
・山内花緒さん 新聞部の部長として、学校の生徒のニーズに合わせた新聞を作るため取材に励んでいます。現代社会で新聞を活用し、教科書より深い理解が得られました。
・小関萌可さん 理科の放射線の授業で新聞を使いました。さまざまな視点の記事が討論の参考になりました。新聞の5W1Hを学んだことが人前で話す時に役立っています。
・松岡賢史朗君 趣味で新聞をスクラップしています。1面はあまり見ませんが、小学生向けの新聞を中心に集め、特に宇宙の記事や少し変わったニュースが好きです。
・尾崎行雄さん 高校生の娘は論説やコラムを読んで記述練習をし、中学生の息子は社会の授業でスクラップをしています。祖父母と新聞を読むのが貴重な交流の時間です。
・高塚陽子さん 新聞は社会を知る情報源で、朝や帰りの会で気に入った記事を紹介しています。授業で活用する際、どこから手を付けたらいいのか分からず困っています。
・稲村明さん 前任校の清水南小がNIE指定校になり、5年生と好きな記事にコメントを付ける取り組みをしました。指定校が終了後、継続できなかったのが反省です。
・矢沢さん NIEの魅力や効果は認められていますが、なかなか広まっていきません。現状や課題をどうみていますか。
・高塚さん NIEの流れに乗れず、実践をためらいがち。記事をどう授業で使おうか悩んでいるうちに、タイミングを逃して悔やむことがあります。多くの実践例を手軽に知る機会があれば、一歩踏み出せる気がします。
・稲村さん 新聞の良さは分かりますが、難しい言葉があるのが活用のネックになっているのではないでしょうか。大人には何ともない語句も、子どもには一つ一つ説明が必要。インターネットなどさまざまな情報ツールがある中、教材として新聞を選ぶときのハードルになっています。
・尾崎さん 保護者の立場から、家庭でのNIEの認知度の低さを感じています。学校から宿題などで働き掛けがない限り、新聞活用への意識は希薄です。学校間、教員間でも温度差が存在している気がします。NIEを実践している教員が異動すると衰退してしまうケースもあり、学校全体での取り組みを考えてほしいです。
・矢沢さん 子どもたちの率直な意見を聞いてみましょう。
・山内さん 所属する新聞部で、全校生徒を対象に新聞に関するアンケート調査を行いました。多くの生徒が新聞を読まないと答えました。「インターネットやテレビで情報に触れているから」「新聞を読む時間がない」という理由が大半でした。新聞の利点を知らないのだと思います。
・小関さん 家庭で新聞をとっていないので読む習慣がないという友だちも多いです。日々のニュースへの関心の薄さも感じます。本も読まず、活字離れは進んでいます。
・松岡君 小学生はまだ、世の中のことを知らなくてもいいと思っています。図書室にある子ども新聞を読んでいる友だちは少ない。新聞に少し、抵抗があると思います。
・矢沢さん 会場で討論をお聞きになった感想をお願いします。
・県NIE研究会会長の望月和彦・静岡由比小校長 NIEを実践している教員は「この記事はあの単元に使える」「この写真を使おう」と、授業につなげて新聞を読んでいます。教材としてどう活用できるかを考える視点を常に持つことが大切です。
・NIEアドバイザーの実石克巳・静岡市立高教諭 そうですね。教材として活用するには長期的な視野で準備を進めていくことが必要。個人の力には限界があり、他の教科の教員や保護者の協力でNIEはもっと広がっていくと思います。
◇……………………◇
□基調提案
■楽しい学びの発見を-角替弘志・大会実行委員長
静岡は、わが国のNIE発祥の地とされています。1985年、静岡市で開かれた新聞大会で、新聞界と教育界が協力したNIE推進が新聞の発展に重要だと強調され、取り組みが始まりました。
言論の自由を踏まえた新聞は、民主主義社会を支える大切な柱。その使命は、教育基本法にある「民主的な国家および社会の形成者」育成を目指す教育の使命と表裏一体です。
社会の風景を伝える新聞は、広く社会に目を向け、さまざまな事象への関心を深めるために便利な素材。テレビやインターネットにも情報があふれていますが、新聞と重ねることで、より的確な情報を把握できます。さらに、いつも容易に、皆と書き込みをしながらでも見られます。
NIE活動が始まる前から、新聞を利用していた教師は少なくありません。教科書とは違う刺激があると知っていたのです。ただ、堅苦しい記事が中心で文字も多く、電子媒体で手軽に情報を得られる状況では敬遠されるかもしれません。しかし実践校の子供たちは、楽しく懸命に取り組みました。重要なのは、まず新聞を手に取る機会を与えること。そこから、面白さや価値を実感できるのです。
活動の活性化には、「NIEはやさしい」と感じ取ることが大切です。「やさしい」とは容易なこと、優しく親しみがあること。「いつも、わくわくするような学びを発見できるやさしいNIE」を旗印に、この大会を新たなステージへのスタートにすることが私たちの願いです。
会場に詰めかけた多くの教育、新聞関係者ら=静岡市駿河区池田のグンシップ
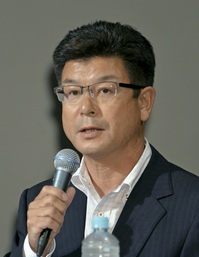
尾崎行雄さん

高塚陽子さん

稲村明さん

基調提案する角替弘志大会実行委員長=静岡市駿河区池田のグランシップ

