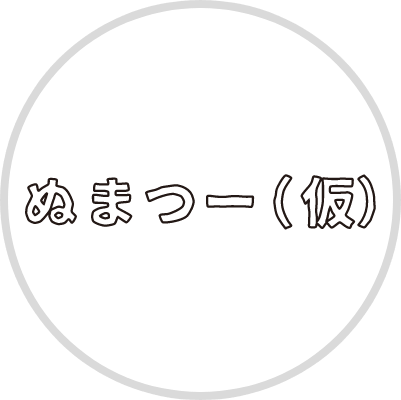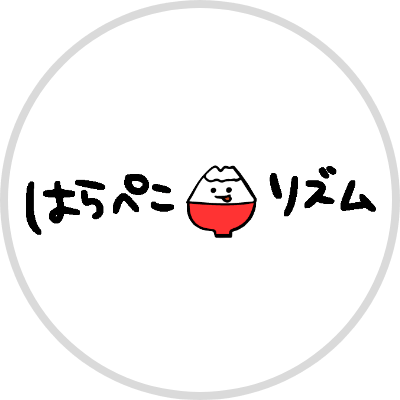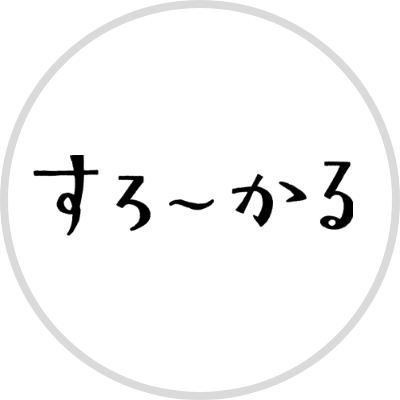症状を自覚しにくい?今、増えている「イヤホン難聴」とは
オンラインの時代だから気にしてほしい!「イヤホン難聴」
リモートワークやオンライン授業などで、イヤホンを使う機会が増えていませんか? 実はその影響で、難聴になる人も増えてきているそうなんです。詳しいお話を「夕刊フジ」「ビジネスジャーナル」等で多数の記事を執筆されている、医療ジャーナリストで薬剤師の吉澤エリーさんにうかがいました。
牧野アナ:「イヤホン難聴」というのは、どのような症状のことを指しますか?
吉澤さん:イヤホンを使用して大きな音を聞き続けることによって生じる難聴のことです。少しずつ進行するため症状を非常に自覚しにくく、気がついたときには難聴がかなり進んでいるケースもあります。
私たちが音を感じるのは、耳から入った音の振動が、内耳の奥の「蝸牛」という器官の内部にある有毛細胞で、電気信号に変換されて脳に伝わり、音として認識されます。その有毛細胞が、大きな音を聞くことで傷ついてしまうんです。そうすると正常に音を信号に変えることができなくなるので、結果として音を感じられなくなり難聴になるのです。
牧野アナ:耳は一度悪くなったら回復させるのが難しいと聞いたことがあるのですが、いかがでしょう?
吉澤さん:おっしゃるとおり、有毛細胞が傷ついてしまうと正常に戻るのが難しいといわれています。
「イヤホン難聴」に治療方法はある?
吉澤さん:基本的には薬による治療になります。炎症ですのでステロイド剤、ビタミン剤、血液の循環をよくする薬などを使用します。あとは薬の治療に合わせて、耳の安静が大事になります。「耳の安静」という言葉は聞き慣れないと思いますが、耳栓などをして耳を音から守ります。症状の進行を防ぐことが最重要となりますので、イヤホンの使用を中断することも大切です。牧野アナ:それもなるべく早めに治療するといいですよね。
吉澤さん:どちらかというと慢性の炎症によって症状が進行してしまうことが多いので、違和感を覚えたらすぐに治療を開始することで改善の余地があると思います。
「イヤホン難聴」で注意すべき兆候は?
吉澤さん:普段耳の感覚なんて気にしないと思うのですが、耳が詰まるような感じや耳の奥がこもったような感じ、もしくは耳鳴りなどがあります。耳の違和感としてはなくても、耳のせいでなんとなく頭痛がするという人もいます。その他「イヤホン難聴」の場合は、高い音が聞こえにくくなるという兆候もあります。高音とはピアノだと鍵盤で一番高いくらいの、4000ヘルツの音など。でもその音が聞こえなくなっても、普段の会話では恐らく自覚できないんです……。牧野アナ:小さなサインをぜひ見逃さないようにしてほしいです。
「イヤホン難聴」にならないよう気をつけるべき点は?
吉澤さん:音が大きいというのが一番の問題なので、音は小さめにするということが大切です。目安としては、イヤホンをしていても人と会話ができる程度の音量が推奨されます。牧野アナ:私もいろいろ考えて、骨伝導イヤホンを使うようにしています。職業柄どうしても耳を使う機会が多くて、耳がちょっと悪くなってきたなと感じ始めているのですが、こういったものは実際はどうなんでしょうか?
吉澤さん:鼓膜を通さず骨の振動を通して聞くというものですが、骨伝導であるにせよ、音は蝸牛に振動が伝わり有毛細胞で信号に変えられるので、医学的エビデンスとして骨伝導イヤホンが難聴のリスクを減らすというものではないんです。
牧野アナ:なるほど、プロセスとしては骨伝導であっても有毛細胞は経由しているわけなんですね。ということは、骨伝導イヤホンだからと安心して音量を大きくするのはダメですね。
吉澤さん:そうですね、音量に気をつける。海外では耳鼻科医などが「60/60rule」、音楽デバイスの音量を総音量の60%までにし、1日あたり60分以内!という注意喚起をしています。仕事などでどうしてもそれ以上使うという場合は、イヤホンを使った時間の3倍は積極的に「耳を休める時間」を作っていただくといいかなと思います。
牧野アナ:耳を休めるというのは、耳栓をするレベルにした方がいいですか?
吉澤さん:本当に気になるのであれば、寝るときに耳栓をして音から耳を守るのもひとつです。基本的には大きな音が影響するので、イヤホンを長時間使った後は意識的に大きな音を避けるようにするといいでしょう。あとは、耳の奥の血流も非常に大事なので、体を温めたり、お風呂に入る。睡眠不足や体調が悪いということも難聴になりやすい傾向にしてしまうので、普段の体力の温存というのもひとつですね。
牧野アナ:やはり耳の対策も、お風呂に入るとか睡眠不足を解消するとか基本的な部分が一番大事なんですね! それによって他の部分の健康にもつながっていきますので、ぜひ実践していってください。
※当サイトにおける情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。記事内容は個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当サイトで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、並びに当社と契約した情報提供者は一切の責任を負いかねます。
免責事項
今回お話をうかがったのは……吉澤エリーさん
薬剤師、医療ジャーナリスト。1969年12月25日福島県生まれ、1992年東北薬科大学卒業(現、東北医科歯科大学)。医療記事を中心に多数メディアに執筆。薬物乱用防止の啓蒙活動、心の問題などにも取り組み、コラム執筆のほか、講演、セミナーなども行っている。吉澤恵理「薬剤師の視点で社会を斬る」ニュース(Business Journal)
SBSラジオIPPO(月~金曜:朝7:00~9:00)忙しい朝を迎えているアナタに最新ニュースはもちろん、今さら人には聞けない情報をコンパクトに紹介!今日の自分をちょっとだけアップデート!番組公式サイトやX(旧Twitter)もぜひチェックを!
radikoでSBSラジオを聴く>