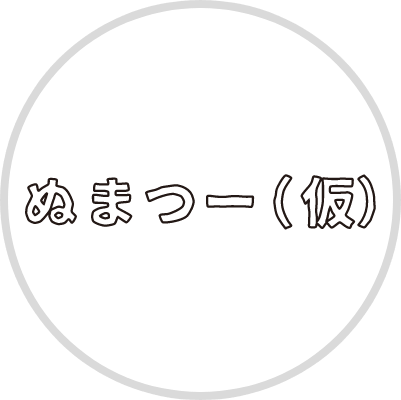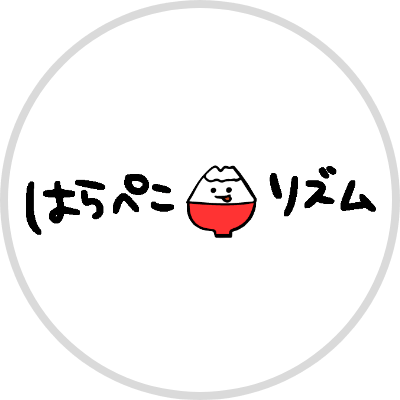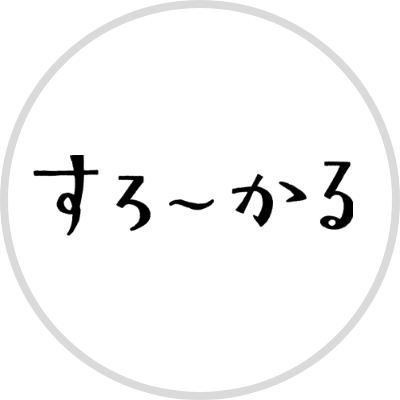ネットで拡散されるデマに騙されないために!正しい情報の見分け方

デマはどうして拡散されてしまうのか?
牧野:赤木さんは2007年に朝日新聞社の『論座』で「『丸山眞男』をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争。」を執筆され話題となりました。それ以後フリーライターとして、貧困問題などを中心に、様々な媒体で執筆を行っていらっしゃいます。デマについてもお詳しいのですが、デマはどうして広がってしまうのでしょうか。赤木:そもそもなのですが、人と話すときに話題は多く持っている方がいいですよね。話題のひとつとして、一番手っ取り早く他人の関心を引きやすいのが、こうしたデマというか、ビックリするような情報です。みんなが知らないようなことを話すことができると、やはり注目を引きやすい、人気を得やすい。そういったことが、デマが広まる土台になっていると思います。
牧野:Youtubeなんかでも収益化したいがために、そういう本当かどうかわからない情報をちょっとセンセーショナルに取り上げて……という人も多いですよね。
赤木:やはり過当競争なのでかなり刺激的な情報をバンバン出して、それで少しでもページビューを稼ごうとするような人も多いです。
インターネットで広がったデマで、有名な事例は?
赤木:いわゆる煽り運転が問題になったじゃないですか。それは2017年の東名高速で起きた煽り運転が発端となったわけですけれども、その事件で容疑者といわれた男性の名字や住所から、その近くにある建設会社を割り出して、そこがその容疑者の父親の会社だという情報が流れて……そこに嫌がらせの電話などが殺到するという問題がありました。牧野:最近SNSでありがちというか、容疑者の名前と同じだったら、そのアカウントが攻撃されてしまうというケースありますよね。
赤木:はい、今回は名字が同じだったという理由なんですが、九州の北の方にはその名字がどうも多いらしいんですね。
牧野:相当迷惑された方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、これは悪意を持って広めているというわけでもないんでしょうか?
拡散する動機は正義?
赤木:むしろ善意だと本人は思っている可能性があるんです。つまりそういう悪いことをした人間や、家族とかを懲らしめてやろうという気持ちですね。牧野:本人にしたら正義なので、そこが厄介ですよね。
赤木:本人は、自分は正しいことをしている、そういう悪質な運転をする人に対して文句を言っているのだと。
牧野:現状なかなかそういう発信を抑えることは難しそうですね……。今度は出てきた情報を見る側がリテラシーを持ってしっかり判断していくということが必要となってくるのですが、デマを信じやすいタイプの人という傾向はあるのでしょうか?
デマを信じやすいタイプの人は?
赤木:社交性の高い人であればあるほど、デマを流しやすい環境にいるとはいえますね。やはり、いろんな人にあれこれ話したい、自分が話す上でいろんな話題を持って、人の関心を引きたいと思えば思うほど、そうしたデマの情報が魅力的に見えてしまうことがありますね。牧野:これは話のネタになるぞと。ある意味、私もそういったポジションにひょっとしたらいるのかもしれませんけども、コミュニケーション能力に自信を持っている人ほど厄介だったりしますね。そういう人は、ある程度自分自身の中でフィルターを持っていたほうがいいですよね。
赤木:自分の中でいったん留めて、その情報の真偽にある程度責任を持たないと。間違った情報を他の人に教えて不利益を与えてしまうことになるので、気をつけて欲しいですよね。
牧野:ここで注意してほしいのが、インターネットの中にももちろん正しい情報はたくさんあるということ。一方で間違った情報も混在しているので、見分けることが重要になります。
デマと正しい話の見分け方のポイントは?
赤木:あまり刺激的な話というのは、気をつけておくべき。一般常識とちょっとずれたようなことは、「知る人ぞ知る、意外な真実」としてすごく魅力的に映るんです。ただそうした情報というのは、大体どこかずれている理由があったりして、そちらの方が正しいというのは実はあまりないんです。基本的には、やはり常識的なことの方が合っていると。もちろん例外もありますが、まずは常識と照らし合わせるということをする必要がありますね。牧野:常識とはずれているけれど、正しいもの。そういうものの見分け方があるのですか?
赤木:基本的な学力や科学的な常識を身につけることです。例えば「食品添加物が体に悪い」という情報がよく流れたりするのですが、食品添加物の安全基準がどのように決められているのかを知っていれば、それほど食品添加物は危険視するようなものではないとわかります。国や科学的な機関が正しい情報を流していますので、そういったエビデンスをもった発信をしている情報を集めるようにしておくことが重要。調べ方をちゃんと知っておくということです。
牧野:我々、報道機関にいると、調べるときには「一次情報にアクセスしなさい」「一番最初にそれを出しているところまでに辿り着くように」と言われますが、そのあたりですかね。
赤木:できるだけ国の出している統計情報などを見る習慣をつけておくと、多少なりともデマに引っかかりづらくなりますね。
牧野:わかりました。いま私たちは、毎日本当に多くの情報に触れています。そんな中でも「個人のフィルター」を持つということが大事になってきそうです。
今回お話をうかがったのは……赤木智弘さん
フリーライター。1975年栃木県生まれ。2007年に『論座』(朝日新聞社)に「「丸山眞男」をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争。」を執筆。話題を呼ぶ。以後、時事問題や貧困問題を中心に執筆活動を行っている。著書に『若者を見殺しにする国 私を戦争に向かわせるものは何か』(朝日新聞出版)、共著として『下流中年 一億総貧困化の行方』(SB新書)など。
SBSラジオIPPO(月~金曜:朝7:00~9:00)忙しい朝を迎えているアナタに最新ニュースはもちろん、今さら人には聞けない情報をコンパクトに紹介!今日の自分をちょっとだけアップデート!番組公式サイトやX(旧Twitter)もぜひチェックを!
radikoでSBSラジオを聴く>
関連タグ